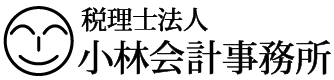事業承継の「脱ファミリー化」が鮮明に

後継者不在率は調査開始以来で最も低い52.1%に
中小企業の後継者問題が長らく課題となるなか、後継者が確保できていない企業の割合が52.1%まで下がり、7年連続で改善したことが分かりました。
帝国データバンク(TDB)による全国調査で、2011年の調査開始以来、最も低い水準です。
27万社を対象に実施された全国調査
今回の調査は、2022年10月~2024年10月にかけて実施され、対象は全業種約27万社。
このうち、後継者が「いない」または「未定」と回答した企業は約14万2千社でした。
コロナ前の2019年と比べれば、実に13.1ポイントの改善となり、後継者不足の問題は緩やかに解消へ向かっているように見えます。
改善の背景には支援の広がり
TDBは、不在率の低下について次のように分析しています。
- 官民の相談窓口が全国的に整備され、情報や支援にアクセスしやすくなった
- 小規模事業者でも利用できる支援メニューが充実
- 自治体や金融機関が事業承継を積極的に啓発したことで、社会全体の意識が向上した
事業承継に関する環境整備が進み、これまで踏み出しにくかった企業も一歩を踏み出しやすくなったことが背景にあるようです。
すべての業種で不在率60%未満は初
調査では、主要7業種(建設・製造・卸売・小売・運輸・サービス・不動産)すべてで、不在率が60%を下回るという初めての結果となりました。
- 最も高かったのは建設業で59.3%
- 最も低かったのは製造業で43.8%
業種による濃淡は残るものの、全体的に改善の傾向が明確になっています。
事業承継は「脱ファミリー化」へ
承継のあり方にも変化が出ています。
2020年以降に代表者が交代した企業のうち、2024年速報値では「内部昇格」が36.4%と最も多く、伝統的に主流だった「同族承継」(32.2%)を初めて上回りました。
さらに、
- M&A や出向などを活用した「M&Aほか」:20.5%
- 社外の人材を招く「外部招聘」:7.5%
と、親族以外への引き継ぎが確実に増加しています。
もはや事業承継は「家族で継ぐもの」という固定観念から離れ、社内外の適任者へ経営を託す時代へ移りつつあるといえます。
後継者不在による倒産は依然多い
一方で、後継者が見つからずに事業継続が困難となる「後継者難倒産」は、2024年1~10月に455件発生。前年同期と同じ水準で、依然として高い状態が続いています。
特に深刻なのが、経営者の病気や急逝により、承継が間に合わなかったケースが189件と全体の4割を占める点です。
TDBは、「事業承継が計画通りに進められず、やむを得ず廃業に追い込まれる企業が今後も発生する可能性が高い」と警鐘を鳴らしています。
まとめ
- 後継者不在率は52.1%と過去最低を記録し、7年連続で改善している。
- 官民の支援体制の整備や意識向上により、事業承継への取り組みが進展。
- 主要7業種すべてで不在率60%未満となり、全体的な改善が鮮明。
- 承継は「内部昇格」が最多となり、同族承継を初めて上回るなど「脱ファミリー化」が進む。
- 一方、後継者難倒産は依然多く、特に経営者の急病・急逝による承継不全が深刻。
この記事は2025年11月に書かれたものです。
内容が最新の情報と異なる可能性がありますのでご注意下さい。