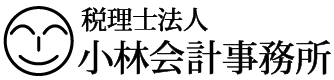相続税調査に「AI時代」到来

相続税調査に「AI時代」到来 ― 国の新たなチェック体制が本格稼働
近年、さまざまな分野で人工知能の活用が加速していますが、税務行政も例外ではありません。
国の税務当局は2025年夏から、相続税の調査対象を選び出すプロセスにAIを本格的に組み込みました。
これにより、申告漏れなどのリスクが高い案件を効率的に抽出し、これまで以上に深く踏み込んだ調査が進められる体制となっています。
すべての相続税申告書をAIが自動評価する仕組みへ
従来も、一部の税目ではAIによる調査必要度の判定が行われていましたが、相続税については今後、提出された申告書を漏れなくAIがチェックします。
各申告データは、リスクの高低に応じてスコア化され、その数値をもとに調査するかどうかを判断する仕組みへと移行します。
このため、AIが「調査が必要」と判断したケースは、従来よりも高い精度で選定されるようになります。
申告件数は過去最高 ― 調査体制強化の背景
2023年(令和5年)の相続税の申告件数は、被相続人ベースで 15万5,740 件。
死亡者全体のうち約 1割(9.9%) が相続税の申告対象に該当し、数字としては過去最高を更新しています。
案件数が増えるにつれ、「どの案件を調査すべきか」を選別する業務に多くの負担がかかっていました。
その課題を解決する手段として、AIによるスコアリングの仕組みが大きく期待されているわけです。
AIが申告内容をスコア化 ― 過去データからリスクを推定
AIがスコアを算出する際には、以下のような幅広い情報が活用されます。
- 過去の税務調査で見つかった申告漏れの傾向
- 多くの申告書や法定調書のパターン
- 財産の種類や価額、負債の内容
- 特定の申告項目の組み合わせによる不整合 など
これらのデータを学習したAIが、0〜1の範囲で細かなリスクスコアを付与します。
この数値が高くなるほど、申告内容に何らかの不自然さがある可能性が高いと判断されます。
AIスコアが「調査手法の選択」にも影響
各地の税務署は、AIが算出したスコアを参考に、
- 実際に訪問して行う本格的な調査
- 書面や電話での確認にとどめる簡易な接触
のどちらを適用すべきかを判断します。
限られた人員の中で効率よく調査を進めるため、AIが意思決定の重要な材料として活用される時代になりました。
相続税は「一度きりの申告」だからこそ、AI活用はより重要に
法人税や所得税のように毎年提出する税目とは異なり、相続税の申告は人生で一回だけのケースがほとんどです。
そのため、税務署側は過去の申告データを蓄積したAIの分析力に頼り、精度の高いチェック体制を構築していく方針です。
すでに法人税・所得税ではAIの導入によって追徴税額が増えるなど、その効果が確認されています。
相続税でも同様に、AIの本格稼働で調査の「質」も「量」もさらに高まると言われています。
税務行政全体のDX推進と連動
法人税や所得税の調査では先行して人工知能(AI)が活用されています。
追徴税額も増加していることからその効果は大きいとされています。
国税庁では、デジタルを活用した手続や業務の在り方の抜本的な見直しとして税務行政の「DX」に取り組んでいく方針を明確にしています(税務行政の将来像2.0)。
その柱の一つが「課税・徴収の効率化・高度化等」で、税務調査にも今後積極的に活用していく方向です。
まとめ
- 2025年夏から相続税調査にAIが本格導入され、全申告書を自動でリスク評価する仕組みが稼働。
- 相続税の申告件数が過去最高となり、案件選別の負担増をAIスコアリングで解消する狙いがある。
- AIは過去の調査データや申告内容の傾向を学習し、不自然さを0〜1のリスクスコアで判定。
- 税務署はスコアをもとに、実地調査か簡易な照会かを判断し、調査効率を大幅に高めている。
- 税務行政全体のDX推進と連動し、相続税でも調査の精度・件数が今後さらに向上すると見込まれる。
この記事は2025年10月に書かれたものです。
内容が最新の情報と異なる可能性がありますのでご注意下さい。